「導入文の書き方に自信がない」「記事を最後まで読んでもらえない」と悩んでいませんか。
せっかく内容にこだわった記事でも、導入文が魅力的でなければ読者の興味を引くことはできません。
この記事では、読者としっかり共感し、自然に「続きを読みたい」と思わせる導入文のコツや失敗しがちなポイント、実践しやすいテンプレートまで徹底解説します。
導入文の書き方を身につけたい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
導入文の書き方で成果を上げるための具体的手順

導入文は記事全体の印象を左右し、読者に本文を読んでもらうための重要なポイントです。
効果的な導入文を書くためにはいくつか大切な手順やコツがあります。
順を追ってポイントを意識することで、より多くの読者にアプローチできる記事作成が可能になります。
読者の悩みや課題を明確にする
まずは、この記事に訪れる読者がどんな悩みや課題を抱えているのかを明確に言及することが重要です。
読者は自分の抱えるモヤモヤや困りごとに共鳴すると、思わず続きを読みたくなります。
具体的には次のようなポイントを押さえましょう。
- 読者像を具体的にイメージする
- 抱えやすい悩みを文章内で言及する
- 現実的なシチュエーションを想像しやすいように描写する
このような工夫により、読者との距離を縮めやすくなります。
共感や信頼感を生み出す表現を使う
読者は自分の気持ちや立場に寄り添ってくれるライターの文章に安心感を覚えます。
「こういう経験ありませんか?」や「○○で悩んだことがある方は多いはず」といった共感フレーズを活用すると効果的です。
また、信頼感を与えるには過度な自信表現よりも、実体験や客観的なデータをさりげなく盛り込むと良いでしょう。
| NG表現 | OK表現 |
|---|---|
| 絶対に~できます! | 多くの方がこの方法で成果を実感しています |
| これ以外考えられません | 私の体験上おすすめできる方法です |
適切な言葉遣いで、読みやすく信頼感のある導入文を意識しましょう。
記事の結論や要点を最初に提示する
読者は「この記事を読むべきか?」を最初の数行で判断します。
そのため、記事の結論や要点をしっかり導入文の中で明らかにしておくことが大切です。
ポイントは簡潔で端的に伝えることです。
- 結論ファーストの構成にする
- 記事の全体像や要点を抜き出す
- 要約しつつも続きを誘う表現を心がける
冒頭で明確に提示することで、読者の興味や知りたい情報をしっかりキャッチできます。
本文を読むメリットを端的に示す
導入文には「この記事を読むと何が得られるのか」というメリットを入れましょう。
たとえば「これを読むことで、導入文作成のコツがわかります」や「初心者でも簡単に実践できるノウハウを解説」のような書き方です。
メリットがしっかり伝わると、読者の「読む意味」が明確になり、最後まで記事を読んでもらいやすくなります。
魅力的なアクション喚起を組み込む
導入文には、自然に読者の行動を促す仕掛けを取り入れましょう。
アクション喚起(コールトゥアクション)は、「まずはこのポイントに注目してみてください」や「具体的な手順を知りたい方は続きをご覧ください」などが効果的です。
焦点を合わせたい箇所や、読者が「次にすべきこと」を分かりやすく示すことで、行動につながりやすくなります。
キーワードを効果的に自然に盛り込む
SEOを意識した記事では、ターゲットキーワードの盛り込みも重要です。
ただし、不自然に詰め込むのではなく「読者の悩み」と「記事の目的」に合わせて自然に挿入しましょう。
たとえば、「導入文 書き方」というキーワードなら、「導入文の書き方ひとつで、記事の成果が大きく変わることも」というように、違和感のない形で配置します。
キーワードの入れすぎには注意し、読みやすさを最優先にしましょう。
導入文を書くときによくある失敗例
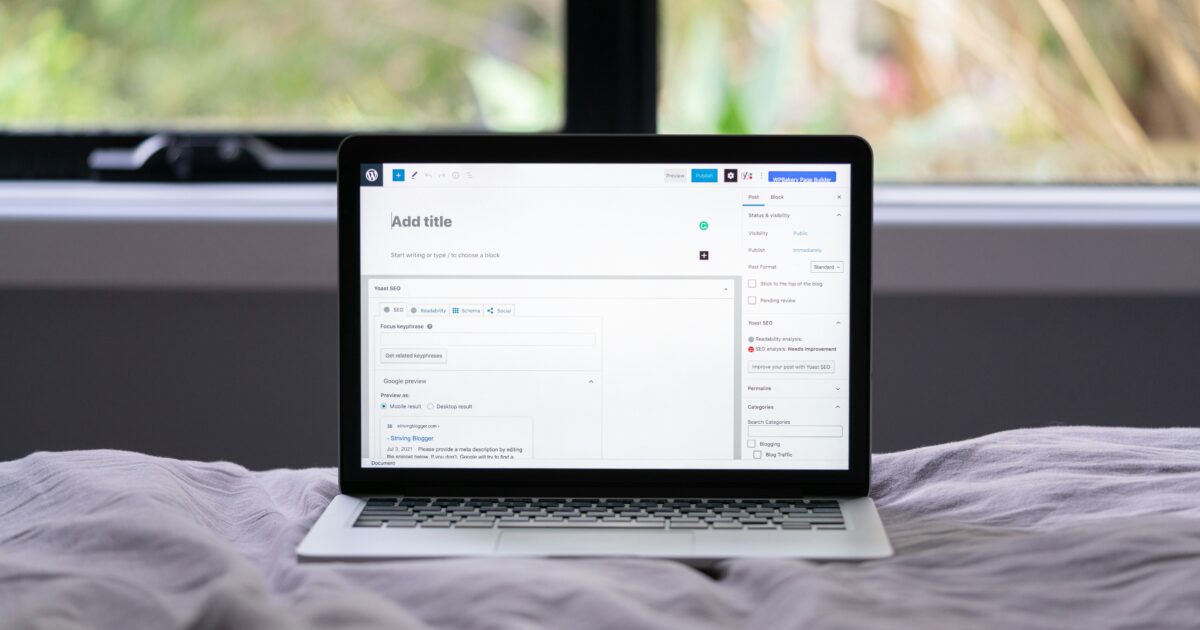
導入文は記事全体の印象を左右する重要なパートですが、せっかく書いてもよくあるミスで効果が半減してしまうことがあります。
どんな点に注意すれば読者にしっかり伝わる導入文ができるのか、代表的な失敗例を知り、対策を意識するだけでも文章の質は大きく変わります。
情報過多で焦点がぼやける
盛り込みたいことが多すぎて、導入文にたくさんの情報を詰め込んでしまうことはよくあります。
ですが、導入文が長くなりすぎたり、話題があちこちに飛ぶと、読者は「結局この記事は何を伝えたいの?」と混乱します。
特に複数の事例やデータ、背景説明などを一度に詰め込むと、かえって文章に芯がなくなりインパクトが弱くなりがちです。
- 伝えたいポイントを一つに絞る
- 情報の優先順位を決める
- 読者の興味を引く内容に厳選する
導入文はあくまで本文への「入り口」として、話題の中心を明確にすることを心がけましょう。
要約だけで終わり印象に残らない
導入文を記事全体の内容の要約や、箇条書きのようにまとめてしまうケースも少なくありません。
このような導入文は情報伝達という面では間違っていませんが、読み手の心に引っかかる要素が少なく、記憶に残りにくいという弱点があります。
| NGな例 | 改善例 |
|---|---|
| この記事ではA、B、Cについて説明します。 | 毎日の業務で悩みがちなA。その解決策としてBやCの視点も重要です。 |
印象に残る導入文にするには、問題提起や読者への問いかけ、共感できるエピソードを盛り込むのが効果的です。
単なる要約で終わらせず、読者の心をつかむ工夫を取り入れるようにしましょう。
専門用語の多用で読者が離れる
専門的なテーマほど、導入文にも専門用語や業界用語を多く使ってしまいがちです。
しかし、こうした言葉の羅列は、初心者や一般の読者にはハードルが高く感じられ、興味を失わせてしまうリスクがあります。
専門用語は、説明や補足を加えるか、できるだけ分かりやすい表現に言い換えることが大切です。
例えば、専門用語を1つ使うごとに、その意味をカッコ書きで補足するだけでも、読者の理解度が大きく変わります。
わかりやすい言葉で読者の目線に寄り添った導入文を意識しましょう。
導入文が効果的になるテクニック集

導入文の工夫ひとつで、記事全体の印象や読者の興味を惹きつける力が大きく変わります。
単なる前置きになってしまいがちな導入文ですが、いくつかのテクニックを活用することで、効果的かつ魅力的な書き出しが実現できます。
ここでは具体的なテクニックの例を紹介します。
数字やデータを冒頭で提示する
読者の注意を一気に集めたいときには、冒頭でインパクトのある数字やデータを示す方法が効果的です。
事実や統計情報を取り入れることで、文章に説得力が加わります。
たとえば「毎日1,000人以上がこのツールを使っています」「約80%の人が〇〇で悩んでいます」など、具体的な数値を出すことで読者はぐっと引き込まれます。
| テクニック | メリット |
|---|---|
| 数字・データを使う | 信頼感・説得力が高まる |
| 抽象的な表現を避ける | イメージしやすい |
記事に信頼性や具体性を加えたいときは、この方法がおすすめです。
ストーリー風の語り口を用いる
文章の始まりで一つのストーリーを展開すると、読者の共感や親近感を得やすくなります。
自分の体験や、身近な出来事、あるいは登場人物を設定して話を始めることで、ぐっと距離が縮まります。
- 昔の失敗談から始める
- 理想の未来を提示する
- 読者と似た状況の人物のエピソードを活用する
この手法は、難しい話題や堅苦しくなりがちな記事にも柔らかさや親しみやすさを与えるのがメリットです。
読み手が自分ごとのように感じやすくなるため、内容への没入感がアップします。
読者に問いかける書き出し
「あなたは〇〇で困ったことがありますか?」など、読者に直接質問を投げかけてから本文を始める方法も効果的です。
問いかけ型の導入は、自然と読者の興味や共感を引き出しやすくなります。
また、自分のことだと感じてもらいやすく、本文への入り口としてスムーズです。
以下は、問いかけを使った導入例の比較です。
| 問いかけ例 | 読者の反応 |
|---|---|
| 「最近、やる気が出なくて困っていませんか?」 | 自分も同じ悩みだと感じて内容に注目する |
| 「ブログのネタ探しに時間をかけていませんか?」 | 自分の行動を振り返るきっかけになる |
問いかけは、内容やテーマに合わせて具体的に設定することがコツです。
導入文の書き方に使えるテンプレート例

導入文の書き方にはさまざまなパターンがあり、ターゲットやテーマによって使い分けることが重要です。
ここでは、よく使われる3つのテンプレートをご紹介します。
悩み提示型
読者の悩みや疑問を最初に明確に提示することで、「自分ごと」として興味を持ってもらえる導入文の書き方です。
この方法を使うことで、読者が記事本文までスムーズに読み進めやすくなります。
- 「こんなことで困っていませんか?」のように問いかける
- 読者が感じているであろう問題や不安をストレートに書く
- 状況や背景も一緒に説明して共感を得る
例えば、「転職活動がうまくいかず不安に感じていませんか?」のような始め方が悩み提示型の典型です。
結論先出し型
テーマに対する結論や要点を冒頭でズバリ伝えるパターンです。
忙しい読者や、早く答えが知りたい人に効果的な導入文の書き方です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 結論が明確で分かりやすい | 文章が冷たくなりやすい |
| 読者の時間を節約できる | 共感されにくい場合もある |
この型では「この記事の結論は〜です」や「答えはシンプルです」のように簡潔に結論から伝えます。
体験談スタート型
自分自身や第三者の体験談から話を始める手法です。
実体験がベースなので、親近感や信頼感を持たせやすいのが特徴です。
例としては、自身の失敗談を語りつつ読者の共感を狙ったり、身近なエピソードから関心を引き出すこともできます。
身の回りの小さな出来事や経験を導入に使うだけでも読む人との距離を縮めることができます。
導入文の書き方を磨くための練習方法

導入文を上達させるには、やみくもに数をこなすだけでなく、効率的な練習方法を取り入れることが大切です。
文章力は、一度身につけば終わりというものではなく、日々の積み重ねや客観的な評価によって磨かれていきます。
ここでは導入文の力を伸ばすための実践的な練習方法について紹介します。
他記事の導入文を写経する
文章力を伸ばす方法のひとつが写経です。
実際に他の人が書いた導入文を、ただ読むだけでなく自分の手で書き写すことで、流れや言葉選び、読者を惹きつける工夫などを体感できます。
この方法は、初心者だけでなく経験者にもおすすめです。
- 気になるブログやメディア記事の導入文を選ぶ
- パソコンやノートに書き写す
- なぜ惹きつけられるのか考えながら写す
写経を繰り返すことで、自然と良いパターンや言い回しが自分の中に蓄積され、オリジナルな文章を生み出す力が養われます。
様々なパターンを書き比べる
同じテーマでも、切り口や表現方法によって読者への印象は大きく変わります。
ひとつの内容に対し、複数の導入文パターンを書いてみることで、自分に合ったスタイルや効果的な書き方を見つけやすくなるでしょう。
| パターン | 特徴 |
|---|---|
| ストレートな説明型 | 内容を端的に伝えたい時に有効 |
| 疑問提起型 | 読者の関心を引きつけやすい |
| ストーリー・体験談型 | 共感を得やすく、親しみを持たれやすい |
このように様々なパターンを意識して練習することが、応用力の向上につながります。
フィードバックを受けて改善する
自分だけで練習していると、どうしても客観性を欠いてしまうことがあります。
他者から意見やアドバイスをもらうことで、自分では気付かなかった課題や改善点を発見できるでしょう。
フィードバックの機会を積極的に活用することで、より精度の高い導入文を書くことができるようになります。
ポイントを整理すると、以下のような流れが効果的です。
- 書いた導入文を第三者に読んでもらう
- 率直な感想や改善案をもらう
- アドバイスをもとに書き直しをする
このサイクルを繰り返すことで、導入文のクオリティアップが期待できます。
導入文の書き方で記事の印象を変える

導入文の工夫ひとつで、記事全体のイメージや読み手への伝わり方は大きく変わります。
どれだけ内容が充実していても、最初の一文で興味を引けなければ読者の離脱を招く原因になりやすいです。
読者に関心を持たれる導入文は、読み進めたいと思わせる力を持っています。
また、記事ごとにターゲットや目的が異なるため、導入文も内容やトーンを調整することが重要です。
適切な切り口や表現を選ぶことで、読者の心に寄り添った印象的な記事に仕上がります。
まとめとして、導入文の書き方を意識することで、記事全体の完成度や読者の評価を高めることができます。




