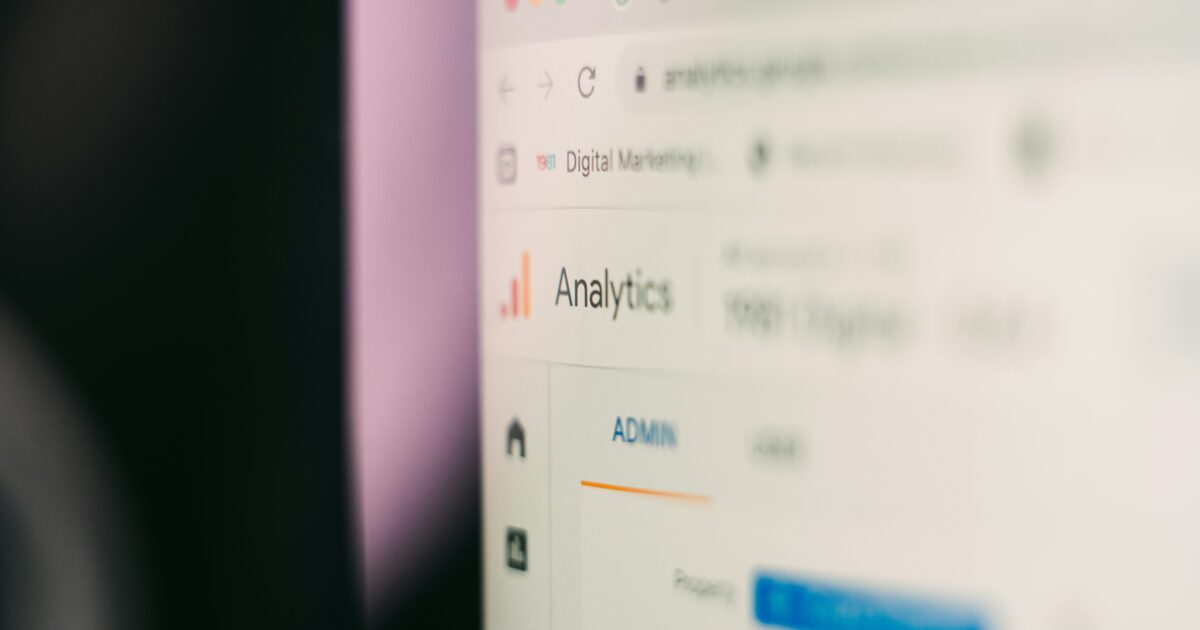長年慣れ親しんだ編集画面が使えなくなる不安は大きいですよね。
クラシックエディタのサポート終了はプラグインやレイアウトの崩れ、編集フローの混乱を招く可能性があります。
この記事では影響範囲の把握から代替エディタの選定、具体的な移行手順と緊急回避策まで、現場で使える実践的な手順をわかりやすく示します。
サポート期限確認、互換性テスト、バックアップやステージング構築といった段取りを項目別に整理しています。
まずは今すぐ確認すべき優先対応リストを提示するので、続きで具体的な作業手順を確認してください。
クラシックエディター終了に向けた対応と代替策

クラシックエディターのサポート終了は、多くの既存サイト運用に影響を与えます。
早めに対応方針を決めることで、突然の表示崩れや編集不能を防げます。
この章では、期限確認から優先対応までの実務的な流れをわかりやすく示します。
サポート期限確認
まず公式アナウンスとプラグインの更新履歴を確認します。
WordPressコアのリリーススケジュールと合わせて、使用中プラグインのサポート終了日を洗い出します。
ベンダーや開発者フォーラムの情報も定期的にチェックする習慣をつけます。
影響範囲把握
影響範囲は単にエディタだけでなく、ショートコード、テンプレート、カスタムフィールドにも及びます。
まず対象サイトの投稿数とページ数、使用中のカスタム投稿をリストアップします。
次に頻繁に使われる編集機能や独自の整形ルールを検証し、優先度を付けます。
リスク評価
リスクはコンテンツ消失、レイアウト崩れ、編集フローの停止など多岐にわたります。
それぞれのリスクについて発生確率と影響度を掛け合わせた優先順位を算出します。
SEOやユーザー体験への影響も評価軸に入れて、定量的に比較可能にします。
代替エディタ選定基準
代替エディタは互換性と学習コストを両立できるかで選びます。
運用規模や編集者のスキル、将来の拡張性を基準にします。
| 評価項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 互換性 | 既存ブロックの表示切替 ショートコード対応 |
| 運用負荷 | 学習時間削減 管理画面の一貫性 |
| コスト | ライセンス費用 導入工数 |
| 拡張性 | サードパーティ連携 将来のアップデート対応 |
移行コスト見積り
移行コストは技術作業時間と検証時間でほとんどが決まります。
具体的にはバックアップ、ステージング構築、プラグインテスト、コンテンツ修正の工数を積み上げます。
外注する場合はディレクション費や想定外のバグ対応を含めた予備費を見込んでください。
小規模サイトなら数日、中〜大規模では数週間から数か月の見積もりが現実的です。
優先対応リスト
影響度の高い箇所から着手することが重要です。
- 公開中の重要ページの表示確認
- 頻繁に更新される投稿群のテスト移行
- ショートコードを多用するテンプレートの対応
- カスタム投稿タイプの互換性検証
- 編集権限とワークフローの確認
緊急回避策
短期的にはClassic Editorプラグインを公式に戻すことが最も手っ取り早い対処です。
ただし永続的解決にはならないため、並行して恒久対応を進めます。
もう一つの方法は、影響の大きいコンテンツだけを手動で段階的に移行することです。
さらに、公開前の編集は一時的に権限を限定し、編集ミスを防ぐ運用も有効です。
移行手順

クラシックエディター終了に備えた移行作業は、段階的に進めると安全です。
ここでは、実務で使える具体的な手順を、バックアップから公開前の確認まで順に説明します。
バックアップ作成
まずはサイト全体のバックアップを取得してください。
データベースとファイル群の両方を別々に保存することが重要です。
バックアップは複数世代を残し、復元テストを必ず実施してください。
外部ストレージやクラウドにもコピーを置き、リスク分散を図りましょう。
ステージング環境構築
本番環境を直接触らず、ステージング環境で作業を進めてください。
ステージングは本番と同一のPHPバージョンやサーバー設定に合わせると検証精度が上がります。
アクセス権は限定し、編集チームだけが動作確認できるように設定してください。
外部連携やSMTPなどもテスト用に差し替えて、誤送信を防止しましょう。
プラグイン互換性確認
まずステージング上で、インストール済みプラグインのリストアップを行ってください。
各プラグインの最新の対応情報を確認し、Gutenbergや代替エディタとの互換性を評価します。
競合が見つかった場合は優先度を付けて対処計画を立ててください。
| チェック項目 | 優先度 |
|---|---|
| アクティブプラグインリスト | 高 |
| 編集画面動作確認 | 高 |
| ショートコード対応 | 中 |
| ウィジェット互換性 | 中 |
コンテンツ移行作業
コンテンツ移行は投稿タイプごとに優先順位を決めて進めてください。
自動変換ツールの利用と手動調整を組み合わせると工数を削減できます。
移行後は表示確認とリンク切れチェックを必ず実施してください。
- 移行対象コンテンツの抽出
- 自動変換の実行
- 手動での微調整
- 確認と承認
特にレガシーなショートコードやカスタムHTMLは手作業で確認すると安全です。
デザイン調整
ブロックエディタではテーマのブロックスタイルが影響しますので、表示崩れをチェックしてください。
必要に応じてテーマの子テーマや追加CSSで調整することをおすすめします。
レスポンシブ表示やフォント・行間など、実際の閲覧環境で確認を重ねてください。
必要ならデザイン側の担当者と共同で微修正を行い、編集者の操作性も考慮しましょう。
公開前動作確認
公開前にはページの表示、フォーム送信、404チェックなどを網羅的に検証してください。
パフォーマンス計測とSEOメタデータの確認も忘れないでください。
問題が見つかった場合は、即時にロールバックできる手順を用意しておくと安心です。
最終的に関係者の承認を得てから本番切替を実施してください。
代替プラグイン比較

クラシックエディター終了に備えて、利用可能な代替プラグインを比較します。
各プラグインの特徴、互換性、導入コストを押さえ、実務に即した選定に役立ててください。
Classic Editor
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 配布元 | WordPress.org |
| 互換性 | 広い |
| 用途 | 従来型編集画面の復元 |
Classic EditorはWordPress公式が提供する代表的な代替策です。
設定がシンプルで、既存の管理画面運用を大きく変えずに済みます。
しかし将来的なサポートポリシーや新機能の追随は限定的で、長期的には別の対応が必要になる可能性があります。
Disable Gutenberg
Disable Gutenbergは名前の通りGutenbergエディタを無効化するためのプラグインです。
特定の投稿タイプだけ無効にする細かな設定が可能で、段階的な移行に向いています。
ただし、プラグイン自体の更新頻度やテーマとの相性を事前に確認する必要があります。
Advanced Editor Tools
Advanced Editor Toolsは従来のビジュアルエディタ機能を拡張する選択肢です。
リッチな編集機能を残しつつ、ブロックエディタとの共存も図れます。
- ツールバー拡張
- テーブル挿入
- フォント管理
- ショートコードサポート
- 互換性モード
編集者に馴染みのある操作感を優先する場合におすすめです。
Classic Widgets
Classic Widgetsはウィジェット画面を従来型に戻すためのプラグインです。
Gutenbergのウィジェット化による表示崩れを避けたいサイトで有効です。
ウィジェットのカスタマイズ性は維持されますが、将来的なAPI変更には注意してください。
Gutenberg Ramp
Gutenberg Rampはエディタの適用範囲を細かく制御するためのプラグインです。
特定の投稿タイプや投稿IDのみでGutenbergを有効化するなど、段階的導入を支援します。
大規模サイトで部分的に新エディタを試験運用したい場合に重宝します。
ただし設定ミスで期待しないページに影響が出ることがあるため、検証環境での事前確認を推奨します。
Editor Plus
Editor Plusはブロックエディタの機能を強化するサードパーティ製プラグインです。
追加のブロックやスタイルオプションを提供し、デザイン表現の幅を広げます。
ブロック中心の運用へ移行する計画がある場合、Editor Plusはコスト効率の良い選択肢になります。
その反面、プラグイン依存度が高まると将来の移行負荷が増えるため、導入前にメリットと制約を整理してください。
互換性テストと問題解決

クラシックエディター終了に伴う互換性テストは、単なる動作確認に留まらず、運用リスクの洗い出しと実際の業務影響を把握する重要な工程です。
ここでは実務的なチェック項目と、問題発見時の優先的な対処法を分かりやすく解説します。
テーマ互換性チェック
まずは現行テーマがブロックエディタに対応しているかを確認します。
外観の編集画面でブロックを挿入し、エディタ上とフロントエンドで見た目の差異をチェックしてください。
functions.phpでadd_theme_supportの設定を確認し、必要ならブロックスタイルやエディタ用のCSSが読み込まれているかを点検します。
子テーマを使っている場合は、親テーマとの上書き関係でスタイル崩れが起きやすいので、子テーマのCSSも検証してください。
不足が見つかったら、エディタ用スタイルを追加するか、テーマ開発者に問い合わせることを検討します。
プラグイン競合解析
プラグイン同士の競合は、エディタ移行で最も発生しやすい問題の一つです。
停止と有効化を繰り返して原因を切り分けする方法が有効で、影響範囲を一つずつ絞り込めます。
WP_DEBUGやQuery Monitorを使い、PHPエラーやデータベースの警告をログで確認してください。
ブラウザの開発ツールも併用し、JavaScriptエラーの有無を調べると発見が速くなります。
- 全プラグイン一括停止テスト
- 段階的な再有効化による特定
- ログ解析とコンソールエラー確認
- 代替プラグインの検討
競合が見つかったら、まずは設定の調整や最新版への更新で解決を試みてください。
ブロック表示確認
ブロックがエディタでもフロントでも正しく表示されるかを念入りに確認します。
保存した投稿を複数のデバイスとブラウザで確認し、レスポンシブ崩れやスタイルの欠落を洗い出してください。
| チェック項目 | 推奨対応 |
|---|---|
| エディタ表示の崩れ フロント表示の崩れ |
追加のCSS適用 テーマのテンプレート調整 |
| カスタムブロック非表示 ブロックの代替表示 |
ブロック登録の見直し サーバサイドレンダリングの確認 |
| 外部ライブラリ競合 スクリプト読み込み順 |
スクリプトの依存関係整理 遅延読み込み設定 |
テーブル内のチェックを基に優先度を付け、まずは表示に直結する問題から対応してください。
ショートコード対応確認
ショートコードはクラシックからの移行で思わぬ混乱を招く要因です。
エディタ上でショートコードが正しく展開されるか、保存後のHTMLにも問題がないかを確認してください。
必要ならショートコードをブロック化するプラグインを導入し、管理しやすくする対策が有効です。
テンプレート内でdo_shortcodeが期待通り動作するか、カスタムフィルタやプラグインの影響も合わせて検証してください。
カスタム投稿確認
カスタム投稿タイプの編集画面やメタボックスの表示が崩れていないか、個別にチェックします。
register_post_typeで’supports’に’editor’が含まれているかを確認し、不足があれば設定を追加してください。
カスタムフィールドやメタボックスが古いコードで作られている場合、Gutenberg対応の書き換えが必要になることがあります。
アーカイブやカスタムテンプレートの表示も忘れず検証し、REST APIが必要な場合はアクセス設定を確認してください。
権限設定確認
エディタ切替により、編集権限が期待と異なる挙動を示すことがあります。
各役割の権限をテストアカウントで実際に操作し、編集・公開・削除が適切に制御されているかを確認してください。
場合によってはMembersやUser Role Editorのようなプラグインで細かな権限調整を行うと安全です。
最後に、変更履歴や監査ログを有効にし、運用中の権限変更を追跡できる体制を整えてください。
運用と保守のポイント

移行後も安定して運用を続けるためには、日々の保守体制を整えることが重要です。
バックアップや更新管理、セキュリティ対策といった基本を押さえれば、トラブル発生時の影響を最小限に抑えられます。
バックアップ運用
まずはバックアップの方針を明確にすることが求められます。
定期的なフルバックアップと差分バックアップの組み合わせを採用して、保管場所と復元手順を文書化してください。
| バックアップ種別 | 頻度 | 保管先 |
|---|---|---|
| フルバックアップ | 週一回 | オフサイトストレージ |
| 差分バックアップ | 毎日 | クラウドストレージ |
| 即時スナップショット | 重要更新時 | オンプレミスとクラウド |
バックアップは定期的に復元テストを実施して、本当に使えることを確認してください。
更新手順管理
プラグインやテーマ、コアの更新は段階的に行うことが安全です。
まずステージング環境で更新を適用し、影響範囲の確認と自動テストの実行を行ってから本番へ反映するとよいでしょう。
更新履歴やロールバック手順は誰でも追えるように記録しておくことが大切です。
セキュリティ対策
攻撃はいつ起きてもおかしくないという前提で対策を講じてください。
定期的な脆弱性スキャンと最小権限の原則に基づくユーザー管理、WAFや二要素認証の導入などを組み合わせることで、防御力が高まります。
セキュリティパッチは優先度を決めて速やかに適用し、影響が大きい変更は事前に関係者へ周知してください。
パフォーマンス監視
サイトの応答速度とリソース使用状況を常時監視する習慣をつけてください。
キャッシュやCDNの活用、画像やスクリプトの最適化を行い、しきい値を超えた場合に通知が飛ぶ仕組みを整えておくと安心です。
定期的な負荷テストを取り入れれば、ピーク時の挙動を事前に把握できます。
編集者教育
運用を安定させる柱は、日々の作業を担う編集者の理解です。
新しいエディタや運用ルールに関して、実践的な研修とハンドブックを用意してください。
- 基本編集操作
- ブロックとショートコードの使い分け
- 画像とメディアの最適化方法
- 権限とワークフローの運用ルール
- バックアップと復元の基本手順
- セキュリティの基本注意点
定期的なハンズオンやQ&Aセッションを実施して、実務で困らない体制を築いてください。
ログと監査
操作ログと監査証跡は、問題発生時の原因追及に欠かせません。
誰がいつ何をしたかを記録し、定期的にレビューする運用を導入してください。
ログの保管期間と閲覧権限を明確にし、不正アクセスや異常な操作を早期に検知できる体制を整えると安心です。
最終判断と推奨アクション

Classic Editorのサポート終了を踏まえ、安定性と運用負荷低減を優先した段階的な移行を推奨いたします。
まずは、全サイトのバックアップとステージング環境構築を最優先で行ってください。
次に、プラグインとテーマの互換性検証を実施し、問題のある箇所は優先度をつけて対応する方針で進めます。
移行は小さなバッチで行い、各段階で公開前動作確認と関係者のレビューを必ず行ってください。
最後に、ロールバック手順と監視体制を整え、リリース後も継続的に改善を続けることを強くお勧めします。